宍道湖育ちのしじみちゃんです!
しじみは目にいい?眼精疲労が抜けない原因と肝機能から整える栄養3つ

「しじみは目にいいって本当?」「眼精疲労が全然抜けないのはなぜ?」「仕事で目が疲れてつらいけれど、食事で手軽にケアできる方法はないの?」
そう思う方もいるかもしれません。
実は、しじみに含まれるビタミンB12・タウリン・オルニチンの3つは、目の疲れの根本に関わる“血流”と“肝機能”を支えるため、眼精疲労の回復に役立つ重要な栄養素です。
この記事では、しじみがなぜ目に良いと言われるのか、眼精疲労が抜けにくい本当の原因、そして肝機能から整えるために注目すべき3つの栄養素について、わかりやすく解説します。
しじみは目にいいと言われる理由

「しじみ=肝臓にいい」というイメージはよく知られていますが、実はその裏で、目の健康とも深くつながっています。私たちの目は、細かいピント調整や光の量の調節を絶えず行っていて、小さな筋肉と神経が休みなく働いています。この働きを支えているのが、血液を通して届けられる酸素と栄養です。しじみには、血液の質や巡りをよくしたり、神経の働きを守ったりする成分が多く含まれているため、「目にいい」と注目されるようになりました。
特に、ビタミンB12やビタミンB2は、視神経や粘膜の健康を支えるうえで欠かせない栄養素です。これらが不足すると、目が乾きやすくなったり、ピント調整に時間がかかったりして、ちょっとした作業でも疲れやすくなります。しじみは、こうしたビタミンを複数まとめて摂れる貴重な食材です。
さらに、しじみに豊富なタウリンやオルニチンは、体の代謝と解毒を支えることで、間接的に目の負担を軽くする働きがあります。目だけを単独でケアするのではなく、「体全体、とくに肝臓の働きを整えることで、結果的に目もラクになる」という考え方に立つと、しじみの価値がより理解しやすくなります。
日々のパソコン作業やスマホ時間で目が重くなったとき、「目薬だけでごまかす」のではなく、体の内側から回復の土台をつくる。その一つの手段として、しじみが選ばれているのです。
しじみ=肝臓だけではないという発想の転換
しじみは長く「二日酔い対策」「肝臓の味方」として語られてきました。しかし、肝臓は摂取した栄養を処理し、必要な形にして全身へ送る役割を担う臓器です。ここが疲れていると、目に必要な栄養も十分に届けられません。つまり、肝臓のケアはそのまま、目への栄養供給を整えることにもつながります。
しじみには、肝臓が行う解毒や代謝の働きをサポートするオルニチンやタウリンが含まれています。このため、「肝臓に良い=間接的に目にも良い」という構図が成り立ちます。肝機能のサポートを通じて、疲労物質が溜まりにくい体をつくることができれば、夜になっても目がどんより重い、といった状態が和らぎやすくなります。
目の疲れと「血流」「代謝」の関係
眼精疲労というと、どうしてもブルーライトや姿勢だけが原因のように語られがちですが、実際には血流と代謝の状態が大きく関わっています。目の奥には毛細血管が張り巡らされており、そこに十分な血液が流れなければ、老廃物が滞り、コリや痛みを感じやすくなります。
しじみに含まれるビタミンB12や鉄は、血液の質を整え、酸素を運ぶ力を支える栄養素です。これらを継続的に摂ることで、目にとって必要な酸素と栄養が届きやすくなり、作業の合間に感じるジーンとした重たさが少しずつ和らいでいきます。
眼精疲労が抜けない本当の原因

目の疲れがなかなか取れないとき、多くの人は「画面を見すぎたから」「年齢のせいだから」と片づけがちです。しかし、実際にはいくつかの要因が重なり合って、慢性的な眼精疲労が生まれています。原因を整理して理解しておくと、なぜ栄養面からのアプローチが必要なのかも見えてきます。
筋肉疲労としての眼精疲労
パソコンやスマホの画面を長時間見続けていると、ピントを合わせるための毛様体筋という筋肉がずっと緊張した状態になります。これは、同じ姿勢で重い荷物を持ち続けるのと同じようなもので、短時間なら問題なくても、毎日続くと疲れが蓄積していきます。
本来であれば、しっかり休息を取れば筋肉の疲労は回復します。しかし、現代の生活では仕事が終わったあともスマホで情報を追いかけ、寝る直前まで画面を見ている人が少なくありません。筋肉が休む時間が短すぎるため、翌朝になっても疲労が抜けきらず、常に「目が重い」「ピントが合うまで時間がかかる」といった状態になってしまいます。
ドライアイや自律神経の乱れ
エアコンのきいたオフィスや、瞬きの回数が減りがちなパソコン作業は、涙の量や質を乱しやすく、ドライアイの原因となります。目の表面が乾くと、わずかな光でもまぶしく感じたり、ゴロゴロとした違和感が続いたりします。こうした不快感は、それ自体がストレスとなり、自律神経のバランスを崩す要因にもなります。
自律神経が乱れると、血管の収縮と拡張がうまくいかず、目の周りの血流も悪化します。血流が悪いと栄養が届きにくくなり、疲労物質もたまりやすくなってしまうため、休んでもすっきりしないという状態に陥りやすくなります。
肝機能の低下と全身疲労
もう一つ見落とされがちなポイントが、肝機能の状態です。仕事や人間関係のストレス、飲酒や不規則な食生活が続くと、肝臓に負担がかかります。肝臓は、老廃物の処理や栄養の代謝だけでなく、ホルモンバランスにも関与しているため、ここが疲れていると、全身のだるさや集中力の低下として表れます。
東洋医学では、古くから「肝は目に通じる」と言われてきました。これは、肝臓の状態が目の疲れや視力の質に影響する、という経験的な知恵を表した言葉です。現代医学的に見ても、肝臓の機能が落ちれば、血液の質や循環に影響が出て、結果的に目のコンディションにも影響することは十分に考えられます。
眼精疲労が「目だけの問題」ではなく、「体全体の疲れの表現」である場合、目薬やマッサージだけでは根本的な改善にはつながりません。ここで初めて、肝機能を含めた内側からのケアとして、しじみをはじめとする栄養補給の重要性が見えてきます。
しじみに含まれる“目と肝機能”を支える栄養3つ

しじみにはさまざまな栄養素が含まれていますが、とくに「目」と「肝機能」の両方を支えるうえで注目したいのが、ビタミンB12、タウリン、オルニチンの三つです。それぞれの特徴と、どのように疲れ目ケアにつながるのかを整理してみましょう。
ビタミンB12:視神経と血液の働きを支える
ビタミンB12は、赤血球の生成や神経細胞の維持に関わる重要なビタミンです。不足すると貧血やしびれ、集中力の低下などが起こりやすくなります。目の健康との関係で見ると、視神経の働きを守り、酸素を運ぶ血液の質を保つことで、目の疲れにくさに貢献すると考えられます。
日々のパソコン作業で目の奥が重く感じるとき、その背景には、視神経にかかる負担や、酸素供給の不足が隠れていることがあります。ビタミンB12を含む食品を継続的に摂ることで、視神経のコンディションを整え、ピント調整の機能を支えやすくなります。しじみは、こうしたビタミンB12を含む代表的な食材の一つです。
タウリン:網膜と代謝をサポートするアミノ酸
タウリンは、エナジードリンクの成分としても知られるアミノ酸で、細胞の代謝や浸透圧の調整に関わっています。目の中では、光を感じる網膜の細胞に多く存在し、その働きを支えています。光の刺激を受け続ける網膜は、非常にエネルギー消費が激しい組織であり、代謝をスムーズに保つことが重要です。
タウリンには、網膜の機能を守り、疲労した細胞の回復を手助けする役割があると考えられています。また、肝臓での胆汁酸の働きを助け、脂質の代謝をサポートすることから、全身の代謝バランスを整える点でも、目の健康に間接的なプラス効果をもたらします。しじみの出汁に溶け出すタウリンを無駄なく摂ることが、疲れ目ケアの一手になります。
オルニチン:肝臓の解毒を手伝い、疲労感を軽くする
オルニチンは、肝臓でアンモニアの解毒に関わる成分で、尿素回路と呼ばれる仕組みの一部として働いています。アンモニアは、体内でタンパク質を分解する過程で生まれる有害物質で、これがうまく処理されないと、だるさや疲労感につながります。
しじみにオルニチンが含まれていることは広く知られるようになり、「疲れたときにしじみの味噌汁を飲むとホッとする」というイメージは、単なる気分の問題だけではないと考えられています。肝臓の負担が軽くなれば、体全体の疲労感が和らぎ、結果として目の疲れもちりやすくなります。夜遅くまで仕事をしたり、飲酒の機会が多かったりする人ほど、こうしたサポート成分の存在は無視できません。
効果を引き出すしじみの摂り方と注意点

栄養素の働きがわかっても、実際にどのように食事に取り入れるかがわからなければ、効果は実感しづらいままです。しじみの良さを無駄なく活かすには、調理法や食べる頻度、体質に応じた注意点を押さえておくことが大切です。
出汁を丸ごと活用する調理法
しじみのビタミンやタウリン、オルニチンの多くは、加熱することで汁の中に溶け出します。そのため、身だけを食べて汁を残してしまうと、本来摂れるはずだった栄養を逃してしまうことになります。しじみの味噌汁やスープを飲むときは、汁までしっかり飲むことが基本です。
また、煮込みすぎると身が固くなり、うま味も失われてしまいます。殻が開いたタイミングで火を止めることで、風味と食感を両立させることができます。味噌を使う場合は、沸騰させると香りや栄養が損なわれやすいため、火を弱めてから溶き入れるとよいでしょう。
一度に大量よりも「少しを続ける」
しじみを食べるとき、多くの人は「たくさん食べたほうが早く効きそう」と考えがちです。しかし、栄養素の多くは、体に蓄えておける量が限られており、大量に摂ってもすぐに排出されてしまいます。目と肝臓のケアを目的とするなら、週に一度まとめて食べるよりも、数日に一度のペースで少量ずつ取り入れるほうが現実的です。
たとえば、朝食にしじみの味噌汁をプラスしたり、休日の昼食にしじみスープを添えたりと、生活リズムに合わせて「続けやすい形」を見つけることがポイントです。習慣化できれば、体の状態もゆるやかに変化していきます。
病気や尿酸値が気になる人の注意点
しじみにはプリン体も含まれているため、痛風や高尿酸血症で治療中の人は、医師の指示に従う必要があります。ただし、日常的な食事で適量を守っていれば、すぐに問題が生じるわけではありません。心配な場合は、摂取量や頻度について、主治医や栄養士に相談しながら調整すると安心です。
また、塩分の摂りすぎにも注意が必要です。市販のしじみ味噌汁の素やだしの素を併用すると、思った以上に塩分量が増えることがあります。減塩味噌を使ったり、だしを薄めにしたりして、全体として無理のない味付けに整えましょう。高血圧や腎臓病を抱えている人は、とくに慎重なバランスが求められます。
しじみ以外で併用すると効果的な目のケア習慣

しじみだけに頼るのではなく、他の食材や生活習慣と組み合わせることで、眼精疲労ケアの効果を高めることができます。日々の暮らしに少しずつ取り入れられる工夫を考えてみましょう。食事でまかないきれない部分があると感じる日は、ルテインやアントシアニンなどのサプリを“補助的に”使うのも一つの方法です。無理なく続けられる形で、目に必要な栄養を整えていくことが大切です。
食事でプラスしたい目に良い食材
目の健康には、ビタミンAやビタミンC、ビタミンE、ルテイン、アントシアニンなども重要です。にんじんやほうれん草のような緑黄色野菜、ブルーベリーやぶどうなどの紫色の果物、アボカドやナッツ類といった食品を、しじみ料理と同じ食卓にのせることで、バランスの良い「目に優しい食事」に。
脂溶性ビタミンは油と一緒に摂ることで吸収が高まるため、オリーブオイルやごま油を少量プラスするのも一つの方法です。しじみの味噌汁に、ほうれん草やわかめを加えるだけでも、栄養バランスはぐっと良くなります。
目の使い方を見直す休憩法
栄養面のケアと同じくらい大切なのが、目の使い方そのものを見直すことです。長時間のデスクワークでは、1時間に1回は画面から目を離し、遠くを見る習慣をつくると負担が減ります。数十秒間、窓の外の景色や天井の一点をぼんやり眺めるだけでも、ピント調整に使われている筋肉が一度リセットされます。
また、意識的にまばたきの回数を増やすことも重要です。集中していると、まばたきが極端に減り、乾燥による不快感が増します。目の周りを温めるホットアイマスクや蒸しタオルも、血流を促し、しじみから摂った栄養が届きやすい状態づくりに役立ちます。
睡眠と生活リズムの整え方
どれだけ栄養を摂っても、睡眠が不足していれば、体が回復する時間が足りません。夜遅くまでスマホを見続ける習慣は、ブルーライトの影響だけでなく、睡眠の質そのものを下げる要因になります。就寝前1時間は画面から離れ、照明も少し落として、体と目を休ませる準備を整えるとよいでしょう。
しじみを使った汁物を夕食に取り入れるのは、心身を落ち着かせる意味でも有効です。温かいスープは副交感神経を優位にし、眠りに入りやすい状態をつくります。肝臓の働きが整い、睡眠の質が上がれば、翌朝の目のスッキリ感にも違いが出てきます。
家族の食卓にそっとプラスできる、頼れるコクヨーのしじみ

毎日の献立づくりって、気づけば同じものが続いたり「もう一品どうしよう…」と迷うことがありますよね。そんな時でも、コクヨーのしじみが冷凍庫にあると本当に便利です。
砂抜き済みでそのまま使えるので、味噌汁やスープに入れるだけでOK。短時間でしっかり出汁が出て、いつものごはんがちょっと丁寧に見えるのがうれしいところです。特別なことをしなくても、普段の食卓に自然と取り入れられる“ラクさ”が続けやすさにつながります。
気負わずに使えるのに、体にうれしい成分もちゃんと摂れるのがしじみの魅力。
宍道湖の特大しじみは贈り物にもおすすめです!大きさに驚きますよ〜
まとめ:しじみを上手に活用して眼精疲労を根本から整える
しじみが目にいいと言われるのは、単に一つの成分が効くからではなく、ビタミンB12やタウリン、オルニチンなどの栄養素が、視神経や網膜、そして肝臓の働きを総合的に支えるからです。眼精疲労がなかなか抜けない背景には、血流の滞りや代謝の低下、肝機能の疲れ、自律神経の乱れなど、さまざまな要因が絡み合っています。
こうした根本的な部分にじわじわと働きかけるためには、一度に大量のしじみを摂るのではなく、日々の食卓の中で無理なく続けていくことが大切です。しじみの味噌汁やスープを定期的に取り入れながら、緑黄色野菜や果物、ナッツなどの目に良い食材も組み合わせ、さらに画面との付き合い方や睡眠習慣も見直していくことで、目のコンディションは少しずつ変わっていきます。
「しじみは目にいいのか?」という問いに対する答えは、「しじみをきっかけに、体全体のケアを見直すことで、結果的に目も楽になっていく」という形で捉えるのが近道です。今感じている夕方のショボショボ感や、翌朝まで残る重たさは、生活を少しずつ整えていくことで、確実に変えていけます。







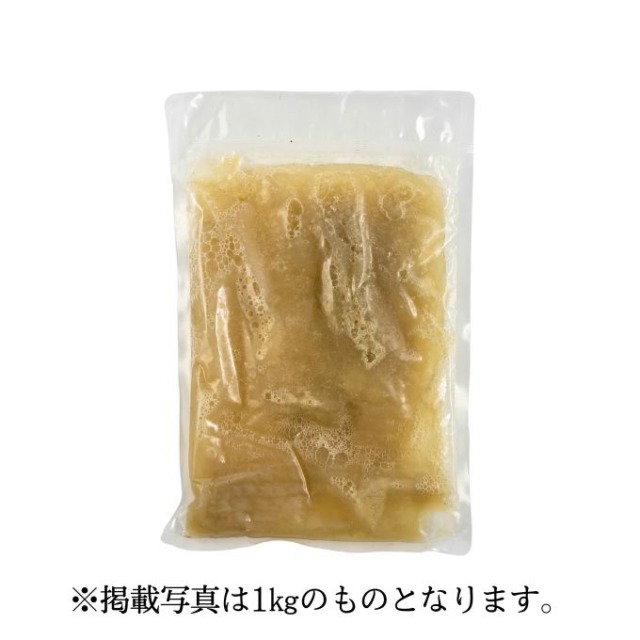





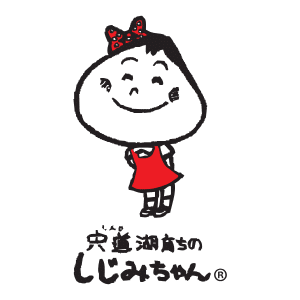









この記事へのコメントはありません。