宍道湖育ちのしじみちゃんです!
「しじみって肝臓に良いって聞くけど、犬にも食べさせて大丈夫なの?」
「味噌汁のしじみを少しあげても平気?塩分とか気になる…」
そう思う方もいるかもしれません。
実は、しじみは正しく調理すれば犬にとっても安全で、栄養価の高い食材です。
ただし、生のまま与えたり、人間用の味付けをしたものをあげるのはNG。
犬の体重や健康状態に合わせた“適量と与え方”を知ることが大切です。
この記事では、犬にしじみを食べさせる際の安全性・注意点・与える量の目安をわかりやすく解説します。
さらに、肝臓ケアに役立つしじみスープの簡単レシピも紹介。
愛犬の健康を守りながら、美味しく取り入れるためのポイントを詳しくお伝えします。
犬にしじみを食べさせても大丈夫?基本の安全性を解説

しじみは、与え方を誤らなければ犬にも利用できる食材です。鍵になるのは、味付けを避けて十分に火を通すこと、殻や砂を取り除くこと、体格に見合う少量から始めることの三点です。人の味覚に合わせた味噌汁や佃煮は塩分や調味料が過剰になりやすく、犬の腎臓や心臓に負担がかかるおそれがあります。まずは無塩で下ゆでした身や、無塩のゆで汁を薄めて使い、体調の変化がないかを観察するのが安全です。
生のしじみは消化に負担がかかるうえ、雑菌や寄生体のリスクを否定できません。必ず加熱してから与えます。人用の味噌汁やめんつゆ、だし顆粒で調えたスープを流用するのも避けてください。塩分だけでなく、玉ねぎ・ねぎ類の薬味が混入していると中毒の心配が出ます。また、殻片は鋭く割れて消化管を傷つける危険があるため、身を外してから細かく刻むのが基本です。砂抜きが不十分なまま与えると下痢の原因にもなります。
初回は「香りに慣らす→ゆで汁をごく薄く→刻んだ身を米粒ほど」の順で段階的に進めると、匂いの刺激や消化負担を抑えられます。与えた後は半日ほど、便の状態や食欲、皮膚の発赤やかゆみの有無を静かに観察します。持病のある犬や、シニアで腎・肝の数値を指摘されている犬は、必ず主治医の方針に合わせましょう。しじみは万能薬ではなく、日々の総合栄養食の「補助」として位置づけると失敗が少なくなります。
しじみに含まれる栄養と犬への効果

しじみは古くから「肝臓に良い食材」として知られており、人間の健康食材という印象が強いですが、実は犬にとっても注目すべき栄養を多く含んでいます。特に肝機能を支える成分が豊富で、疲労や老化に伴う代謝の衰えをケアしたい犬に適しています。
オルニチンによる肝臓サポート: オルニチンはアミノ酸の一種で、アンモニアを分解する働きを助けます。犬でも肝臓の負担を軽減し、老廃物の代謝をサポートします。
タウリンと鉄分の効果: タウリンは心臓や目の健康を維持し、鉄分は酸素を運ぶ赤血球を助けます。どちらも体力維持に欠かせません。
ビタミンB群による代謝アップ: B12などのビタミンB群は、食事から得た栄養をエネルギーに変える働きを促します。エネルギー代謝がスムーズになり、元気な毎日を支えます。
ただし、どれほど栄養価が高くても、過剰に与えれば逆効果です。鉄分やたんぱく質を摂りすぎると臓器に負担を与えることもあるため、少量をバランスよく取り入れるのが理想です。
犬にしじみを与える際の正しい方法と量の目安

まず、しじみは必ず加熱します。砂抜きを丁寧に行い、殻を洗ってから水から火にかけ、沸騰後数分で火を止めましょう。ゆで汁と身の両方を冷ましてから与えます。最初はごく少量から始め、反応を見ながら量を調整します。
体重別の目安: 小型犬(〜5kg)で小さじ1、中型犬(10〜15kg)で小さじ2、大型犬で小さじ3〜4が上限です。週2〜3回程度を目安にしましょう。毎日のように与える必要はありません。
冷凍保存する場合は、小分けして氷皿などで保存すると便利です。一度解凍したものは再冷凍せず、その日のうちに使い切るようにしてください。
しじみを使った犬用レシピ|スープ・出汁・お粥
しじみは「肝臓をいたわる食材」として知られています。含まれるオルニチンやタウリン、鉄分、ビタミンB群は、老廃物を分解する肝臓の働きを助け、疲労回復や代謝アップに役立ちます。特に、薬を服用している犬やシニア犬では、こうした栄養が穏やかに体を支える効果が期待できます。
とはいえ、実際に自分でしじみ料理を作るのは少し難しそうだと感じる方も多いでしょう。ここでは、手作りの簡単な方法に加えて、市販のしじみ入り食品を上手に取り入れるコツも紹介します。
簡単しじみスープの作り方
まずは最もシンプルなしじみスープ。砂抜き済みのしじみを鍋に入れ、水から火にかけます。殻が開いたら中火で2〜3分煮て、火を止めて冷まします。人間用の味付けは不要で、塩・味噌・出汁を加えると塩分過多になるので避けましょう。
スープは冷ましてから、体重5kgの小型犬なら小さじ1〜2を目安に与えます。残りは製氷皿に入れて冷凍保存し、1回分ずつ解凍して使うと衛生的です。
胃腸に優しい|しじみのお粥レシピ
体調が優れない犬やシニア犬には、しじみ出汁を使ったお粥がおすすめです。
炊いたご飯にしじみスープを加えて再加熱し、火を止める直前に刻んだしじみの身を少量加えます。
よく冷ましてから与えましょう。にんじんやかぼちゃを少し加えると、自然な甘みが出て食べやすくなります。
しじみの香りが食欲を刺激し、食が細い犬でも口にしてくれることが多いです。
手軽に続けたいなら市販のしじみ入り食品も
最近では、犬用の「肝臓ケアフード」や「しじみエキス入りサプリ」も登場しています。
オルニチンやタウリンを配合したドッグフード、しじみエキス入りのおやつなどを取り入れれば、毎日のごはんで自然に栄養を補えます。
特に忙しい日や調理の手間を省きたい場合に便利です。選ぶときは「犬用」「無添加」「国産」の表記があるものを選ぶと安心です。
手作りでも市販でも、重要なのは「塩分を避ける」「少量から試す」「継続しやすい形で続ける」こと。
無理のない範囲で、しじみの栄養を愛犬の健康維持に取り入れていきましょう。
しじみサプリやフードで手軽に栄養を補う方法
繰り返しになりますが、調理の手間を省きたい場合は、しじみエキスを使った犬用サプリやフードを活用する方法もあります。オルニチンやタウリンを配合した製品は、肝臓ケアを意識した内容になっています。
選ぶときは「犬用」「無添加」「国内製造」を確認し、信頼できるメーカーのものを選びましょう。体調や年齢に合わせて量を調整し、効果を焦らず長期的に観察することが大切です。
犬にしじみを与えるときの注意点とNG例

生のしじみや味付きのしじみは避けましょう。加熱していないものには雑菌や寄生虫のリスクがあり、味噌汁などの塩分は腎臓に負担をかけます。
また、殻や砂が残ったままだと消化器を傷つける危険があります。砂抜き・殻取りを徹底し、細かく刻んで与えましょう。
過剰摂取もNGです。栄養が偏ると臓器に負担がかかるため、週に2〜3回、少量を心がけましょう。アレルギー反応が出た場合はすぐに中止し、獣医師に相談してください。
まとめ|しじみを上手に取り入れて犬の健康を守ろう

しじみは、肝臓を支えるオルニチンやビタミンB群など、犬の健康維持に役立つ成分を豊富に含んでいます。適量を守って調理し、日々のごはんに少し加えるだけで、食事全体の栄養バランスが整います。
ただし、生食や味付きのしじみはNG。安全な方法で少しずつ取り入れることがポイントです。便利な冷凍保存やサプリも活用しながら、無理なく続けることが健康管理の第一歩になります。
コクヨーのしじみを使って、安心・新鮮な栄養を

犬に与えるしじみを選ぶなら、島根・宍道湖産の生しじみをおすすめします。
なかでも「コクヨーのしじみ(宍道湖産・砂抜き済み)」は、朝獲れを冷蔵便で直送する高品質なしじみです。
丁寧な砂抜き済みで、届いてすぐに使えるのが特長。身はふっくら肉厚で出汁も濃く、旨みが強いため、しじみスープや犬用お粥にもぴったりです。
冷凍保存も可能で、必要な分だけ小分けして使えるため、衛生的に管理しやすいのも魅力。
スーパーではなかなか手に入らない鮮度と香りを、産地直送でご家庭へ。
愛犬にも安心して使える素材で、毎日の食卓をもっと健やかに彩りましょう。







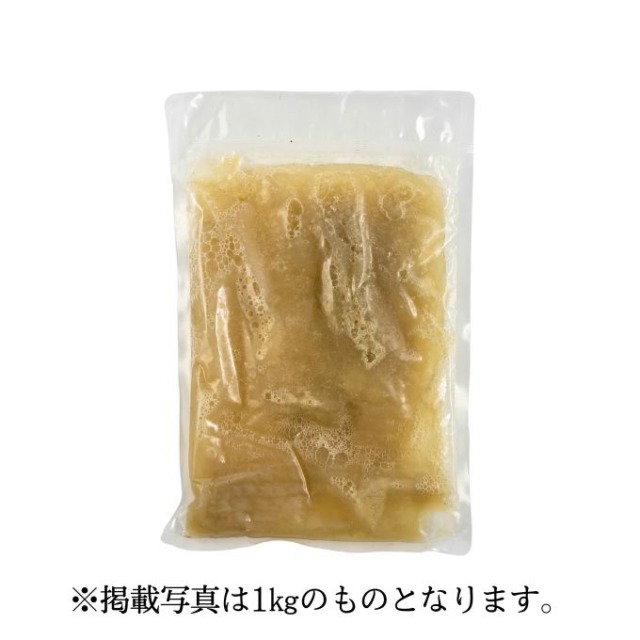




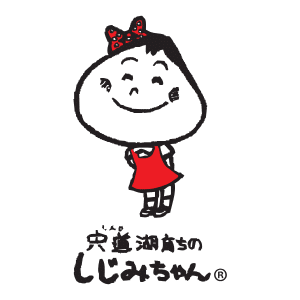








この記事へのコメントはありません。