宍道湖育ちのしじみちゃんです!!
「宍道湖七珍って、どんなものなの?」
実は、宍道湖七珍の中でも“しじみ”は栄養価・旨みともに群を抜く存在で、昔から健康と長寿を支えてきた日本の伝統食材です。日々の疲れや肝機能のケア、血圧のコントロールにも役立つとされ、現代人の食生活にも欠かせない一品といえます。
この記事では、「宍道湖七珍」とは何かという基本から、しじみが特別視される理由、健康効果や栄養成分、家庭でおいしく取り入れる方法までを詳しく解説します。さらに、比較的簡単に入手・調理でき、ご自宅でも本場の味を楽しめるしじみの活用法についても紹介していきます。
宍道湖七珍とは?起源と定義

宍道湖七珍は、宍道湖とその水系が育んできた代表的な魚介を七つにまとめ、地域の味を象徴的に語るための呼称です。七という数は覚えやすく、旅人にも地元の人にも通じる“共通言語”として機能してきました。七珍という枠組みは固定の銘柄表ではなく、時代や資料、漁の状況によって顔ぶれがわずかに入れ替わることがあります。むしろその可変性こそが、湖の表情や暮らしの変化を映す“生きたラベル”としての魅力なのです。朝の湖に立つ風の冷たさ、川が運ぶ栄養、海から忍び込む潮の気配。そうした自然の呼吸が一年を通じて交じり合い、器のなかに季節の輪郭を描きます。七珍は、その輪郭を言葉と皿で共有するための仕組みだといえるでしょう。
七珍が名物で終わらないのは、食材単体ではなく、漁の暦、保存や調理の知恵、もてなしの作法までを含む“文化のまとまり”として受け継がれてきたからです。日々の汁椀から晴れの席のご馳走まで、場と季節に応じて置きどころがあり、味わいの強弱の調整がある。旅で出会った一皿が記憶に残るのは、味の背後にこうした暮らしのリズムが響いているからにほかなりません。かつて旅人の土産話だった七珍は、いまや郷土の誇りとして地域の基礎知識にまで浸透し、子どもたちも自然に名前を覚えていきます。家庭料理とハレの膳、その二つの顔を併せ持つ柔らかさが、七珍の懐の深さを物語っています。
七珍を知る:それぞれの特徴と魅力

| 七珍 | 別名・読み | 概要(分類・特徴) | 旬の目安 | 向く料理 |
|---|---|---|---|---|
| しじみ | 蜆/しじみ(ヤマトシジミ) | 汽水域の二枚貝。コハク酸由来の旨み | 夏・冬 | 味噌汁、澄まし、炊き込み |
| すずき | 鱸/すずき | スズキ科。香りが立ち身はしなやか | 初夏〜夏 | 塩焼き、吸い物、刺身 |
| うなぎ | 鰻/うなぎ | ウナギ科。脂の甘みが深い | 秋〜初冬(天然)※土用は習俗 | 蒲焼き、白焼き |
| しらうお | 白魚/しらうお | サケ目シラウオ科。繊細で透明感 | 晩冬〜早春 | 卵とじ、吸い物、天ぷら |
| こい | 鯉/こい | コイ科。旨み厚く野性味あり | 冬 | あらい、甘露煮 |
| もろげえび | — | 宍道湖周辺の小型エビ(地域名) | 夏〜初秋 | 天ぷら、唐揚げ |
| あまさぎ | ワカサギ(地域名) | キュウリウオ科ワカサギ属 | 冬〜早春 | 唐揚げ、南蛮漬け、天ぷら |
宍道湖の魚介は、香りが澄む・甘みがにじむ・余韻が長いのが特徴。どれか一つが突出するのではなく、三つが重なって後味に静かに残ります。調理の基本は“素材の声を大きくしすぎない”こと。香りを立てたいなら焼く、旨みを重ねたいなら煮る、食感で弾ませたいなら揚げる、そして全体の調和を取りたいなら味噌汁や澄ましなどの汁物に仕立てる。この整理だけで、家庭の献立設計がぐっと楽になります。
宍道湖という舞台――汽水湖が育む味の個性
宍道湖は淡水と海水が出会う汽水湖です。完全な淡水でも海水でもない中間の環境は、生き物にとって微妙な調整を強いる一方で、身質や旨みを鍛える舞台になります。季節や気象によって塩分や水温、栄養塩のバランスが揺らぎ、その“適度な負荷”が代謝を刺激し、グリコーゲンやアミノ酸の蓄積に影響します。結果として“軽やかなのに芯がある”味の輪郭が生まれるのです。春はやわらかく、夏は力強く、秋はまろやかに、冬は引き締まる。同じ食材でも季節で表情が変わり、最適な調理も移ろいます。風向きや雨量、月齢ですら漁のリズムに影響し、持続可能な漁の手立ては湖の未来の味をも支えています。

こうした環境の中で育つ魚介は、器に盛られたとき、湖の景色を背負って立ち上がります。焼き物の香りには風が通り、椀の湯気には朝の水面の透明感が宿ります。味覚だけでなく、五感の記憶を呼び覚ますからこそ、旅人は帰ってからもふっと思い出し、再び宍道湖の味を探しに来るのです。
季節と行事に息づく“七珍の食文化”

宍道湖七珍は暦とともに楽しむのが本来の姿です。初物は香りが軽やかで、素材の輪郭を確かめる時期に向きます。盛りの時期は力が充実し、調味を抑えても皿がよくまとまり、名残になると深みが増して、煮物や甘露煮のように旨みを重ねる料理に落ち着きが生まれます。家庭では、最初と最後に椀を配して全体を整えることが多く、もてなしの席でもその流れは変わりません。行事や祝いの席に七珍が寄り添うのは、単に豪華だからではなく、季節の意味づけと相性がよいからです。春先の節目には軽やかな椀、夏には香ばしい焼き物、秋には実りに呼応する煮物、冬には体を受け止める温かな汁。役割が整理されていれば、準備は段取りよく進み、もてなす側にも余裕が生まれます。
七珍はむりに全部そろえなくて大丈夫。季節のものを一品だけでも食卓は十分“宍道湖らしく”なります。しじみの味噌汁や唐揚げなど家庭でも簡単にできそうな宍道湖産の食材で七珍を楽しむことができます。
要となる「しじみ」——香り・旨み・役割

七珍はそれぞれ個性がありますが、食卓としてまとまりを出すには“軸”があると楽です。そこで頼りになるのが、しじみの味噌汁や澄まし。香りはすっきり、味は出しゃばらず、あと口にやさしい甘みが残ります。主菜の前に少し口を整える一杯としても、最後に余韻を軽く締める一杯としても便利です。味噌仕立てなら満足感が出て、澄ましなら香りの輪郭がくっきり。どちらも煮立てすぎないのがコツで、貝が開いたら火を落とす、味噌は火を止めてから溶く、澄ましは塩味を控えめに——そんな小さな作法が、澄んだ一杯につながります。
料理との合わせ方もシンプルです。すずきの焼き物の前には軽い澄まし、うなぎの力強い脂には塩分控えめの味噌仕立て、しらうおの繊細な一皿には極薄の塩味で出汁を立て、こいの甘露煮のあとには生姜を少し利かせた一杯で後味を整える。しじみの味噌汁や澄ましは主役を奪わず、料理同士をやさしくつなぐ存在です。だから、家庭で七珍を楽しむときも、はじめの一杯が良い導線になります。
現地で堪能 松江市内で宍道湖七珍

松江市には、季節のうつろいに合わせて宍道湖七珍を出す店がいくつもあります。旅の食事でも地元の日常でも、器の前でふっと立つ湖の香りから始まり、焼き物・煮物・揚げ物へ続く流れの中で、それぞれの魚介の個性が自然に顔を出します。観光なら土地の物語に触れる一皿として、暮らしの場では「今日はこれを」と選べる気軽さも。同じ七珍でも時期が変われば香りも余韻も違い、その振れ幅こそが松江で味わう楽しさです。
手軽に楽しめる“宍道湖産しじみ”お取り寄せ

旅の余韻を、明日の一椀から。産地で選別と砂抜きまで整えた宍道湖産しじみを小分け冷凍で常備すれば、解凍を待たずに必要な分だけ鍋へ移せます。火加減は中火からゆっくり、殻が開いたら弱めてアクを静かに払うだけ。冷凍によって出汁の抽出がよくなるため、味噌や塩は控えめでも澄んだ旨みが立ち上がります。朝は軽い味噌椀で体を起こし、夜は雑炊やスープで余韻をやさしく整える。こうして“七珍の序章”を日常に据えると、主菜や副菜がどれであっても食卓に一本の芯が通ります。
はじめての方には少量パックが扱いやすく、家族で続けるなら容量を上げると無駄が出ません。椀物中心なら小〜中粒、炊き込みやパスタに広げるなら中〜大粒が使いやすいでしょう。コクヨーオンラインショップでは、粒サイズや容量の選び方、保存のコツ、簡単なレシピまでひとまとまりに案内しています。届いたその日から、宍道湖の“澄み”をあなたの台所で再現できます。まずは“明日の一椀”から始めてみてください。しじみが常備されているだけで、平日の食卓にも落ち着きと清々しさが生まれ、宍道湖七珍の世界がいつでも開きます。
美味しい宍道湖産しじみをお届けします!
まとめ——湖の設計図を日常の食卓へ
宍道湖七珍は、環境と暮らしが織り上げた文化の結晶です。代表的な七つの魚介には、それぞれの個性と役割があり、器の前に立つと湖の景色がふっと立ち上がります。現地で触れた一皿の記憶は、しじみの椀でやさしくよみがえります。小さな器を日常に重ねることは、特別なご馳走を毎日に引き寄せることではなく、暮らしのリズムを静かに整えることです。今日の一椀、明日の一椀。その繰り返しのなかで、宍道湖の風は食卓を通り抜け、日々の時間に澄んだ余韻を残していくでしょう。







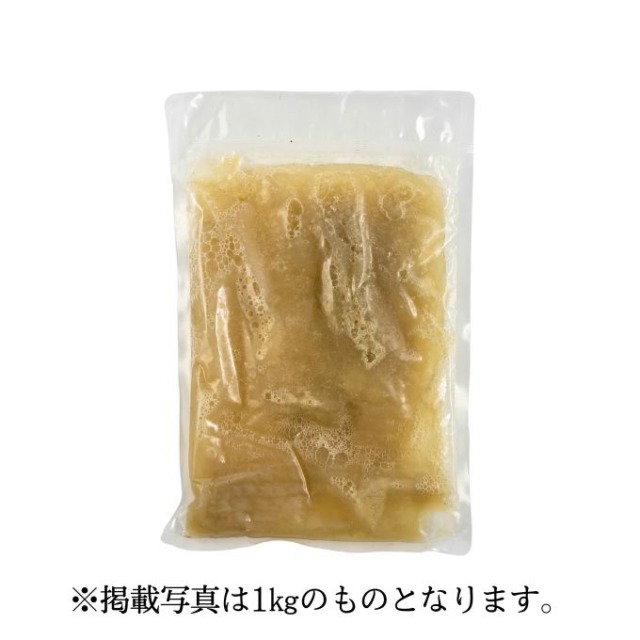




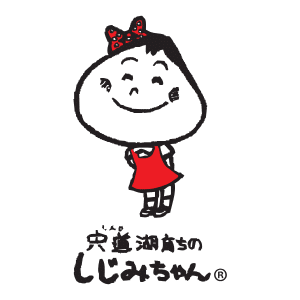








この記事へのコメントはありません。